―鞄製作の手順―
ご注文をいただいてから鞄が完成するまでの製作工程をご紹介します。
スケッチ作成、型紙製作、裁断、縫製、そして仕上げ・包装まで——
ひとつひとつの工程を経て、心を込めて丁寧に仕上げていく様子を、ぜひご覧ください。
スケッチ作成
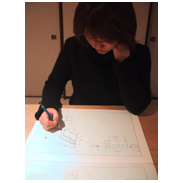
ご依頼いただいた鞄を形にするため、まずはスケッチを描きます。
この工程はとても重要で、鞄の出来栄えを大きく左右します。
ラフスケッチと詳細スケッチを使い分けながら、理想の鞄に近づけていきます。
いつも使うのは、A3サイズの5mm方眼紙。まるで写真のように、その紙面に描きためていきます。
その中から、「これだ!」という“光る鞄”が生まれたときに、ようやく製作へと進むのです。
……とはいえ、これがなかなか一筋縄ではいかず。
踏ん切りをつけるまでに、ものすご〜く時間がかかるのが常です。
なにせ、仕上がった鞄はご依頼くださったお客様の手に渡るわけですから、慎重にもなります。
気がつけば、鞄のデザインをしていたはずが、いつの間にか家具のスケッチになっていた…
なんて路線変更もしばしば。思案に暮れる時間もまた、ものづくりの一部なのかもしれません。
⇩
型紙製作

決定したスケッチをもとに、さらに詳細な設計を行い、型紙を作成します。
これは、実際に革を裁断するための「下敷き」のようなもの。
そのため、厚手の紙に力を込めつつも、丁寧に、そして慎重に形を写していきます。
この工程でやり直しが入ることも、実はよくあります。
型紙の精度は、そのまま鞄のスタイルや完成度に直結するため、少しずつ微調整を重ねながら、美しい仕上がりを目指します。
⇩
革の検品

使用する革を見定める作業です。
左の写真では、購入した革を荷解きしながら検品をしているところです。
革は何枚か重なった状態で筒状に巻かれ、送られてきます。
まずはそれを丁寧にほどき、1枚ずつ巻き直しながら、じっくりと革の状態を確かめていきます。
検品しているのは、牛の半頭分にあたる大きな革。
革を広げている作業台は、実は1m×2mものサイズがあるのですが、それよりもずっと大きく、存在感たっぷりです。
大きな革を相手にしながら、小さな傷やシワ、厚みのムラなどを見逃さぬよう目を凝らします。
⇩
裁断
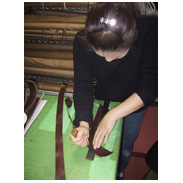
決定した「革」を、いよいよ裁断します。
型紙や金定規に沿って、専用の「革包丁」を使い、必要な寸法に切りそろえていきます。
このとき最も重要なのは、「革の性質を見極めること」。
強度に優れた部分、表面が美しい部分、加工しやすい部分、裏地に適した部分……
革の一枚一枚に個性があるため、それぞれの特性を活かすように型紙を配置します。まるでパズルを組むような作業です。
極小の部品を除き、裁断はすべて「手作業」で行います。
また、専用の工具を用いた型抜き作業も、この工程に含まれます。
⇩
漉き
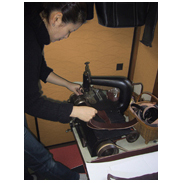
裁断した革の接合部分に対して、「革漉き機(かわすきき)」を使って厚みを調整します。
この工程は、全製作工程の中でも最も重要で、そして最も難しい作業のひとつです。
わずかな厚みの違いが「鞄の出来映え」に直結するため、特に神経を使います。
厚すぎても薄すぎてもダメ。やり直しがきかない、失敗の許されない作業です。
革の切り返し部分や折り込みのために行う処理で、聞き慣れない言葉かもしれませんが、革の裏側を“削ぐ”ようにして厚みを整えます。
簡単に言えば、各パーツの下処理、いわば「仕込み」のようなもの。
ここがうまくいかないと、この先すべての工程に響いてくる、まさに職人の腕の見せどころです。
⇩
パーツの下処理(折込・へり返し)

漉きをかけた革のパーツたちを、丁寧に「糊付け」し、折り込んでいく作業です。
これは、ミスのない縫製を行うための大切な下準備でもあります。
ゴム糊は専用のヘラを使い、薄く均一に伸ばしながら塗布していきます。
しっかりと乾燥させたあと、型紙をあてながら直線部分はそのままに、曲線部分はヒダをとりつつ丁寧に折り込んでいきます。
折り込みが済んだら、軽く金槌で叩いてなじませた後、ローラーをかけて、まんべんなく圧着させます。
見えない部分にこそ、手間と気遣いを惜しまず。鞄の仕上がりを左右する、小さな積み重ねです。
⇩
パーツの下処理(コバ塗り)

裁断した革の切り端(=コバ)に、「バスコ」を塗り込んでいきます。
これは、切り口の毛羽立ちを防ぎ、見た目にも美しく仕上げるための大切な工程です。
塗り作業は、はみ出さないように細心の注意を払いながら、丁寧に、丁寧に進めていきます。
少しでも気を抜けば、すぐにムラやはみ出しが出てしまうため、集中力の要る作業です。
また、仕上げとしての役割に加え、デザインの一部として、コバにバスコで色を入れることもあります。
鞄の印象をさりげなく引き締めてくれる、隠れた名脇役といえる工程です。
⇩
縫製

裁断した革を、「腕型工業用ミシン」で縫っていきます。
使用する針の形状や太さ、糸の太さ、ステッチのピッチ(間隔)、上糸と下糸の張り具合など――
ひとつひとつを鞄の仕様に合わせて調整しながら、丁寧に縫製していきます。
革の厚みや質感によって、ミシンの挙動も微妙に変わるため、常に手元の感覚に集中して作業します。
シンプルな工程に見えて、実は経験と勘がものを言う場面です。
⇩
仕上・検品

ここまでで、鞄はほぼ完成の状態となります。
この段階で、全ての工程を改めて見直し、最終チェックを行います。
お客様のもとへお届けして本当に良いものかどうか――細部まで入念に確認します。
チェック中も、革に傷がつかないよう細心の注意を払います。
そのため、作業中は爪を伸ばすことも、マニキュアをつけることも厳禁。些細なことであっても、仕上がりに影響する可能性があるからです。
完成した鞄のサイズに合わせて、専用の布袋を製作。
この布袋に鞄を丁寧に収め、さらに梱包して、ようやく全ての工程が終了します。
そして最後に――
鞄が無事に届きますように。
気に入っていただけますように。
少々大げさかもしれませんが、いつも心の中で小さく祈りながら、発送手続きを行っています。
